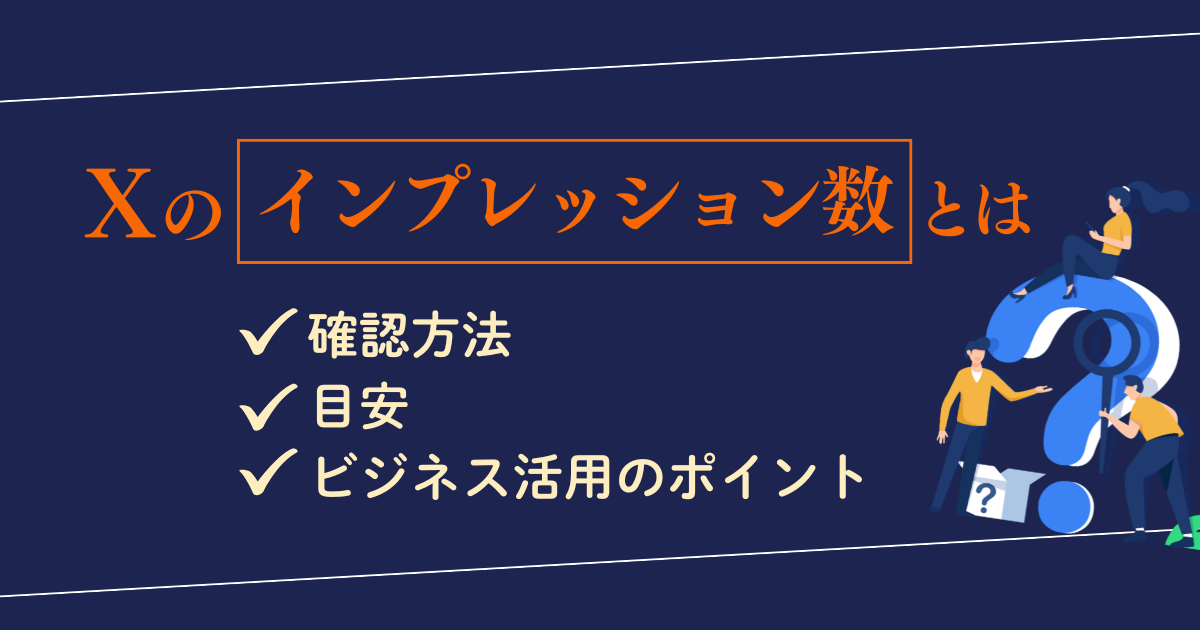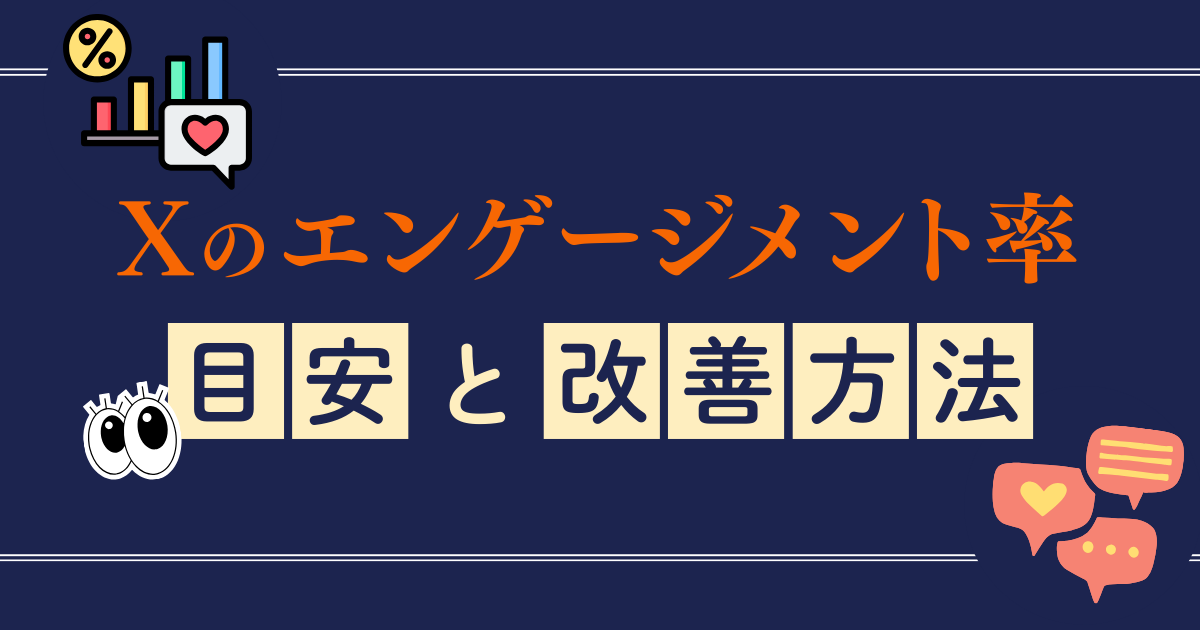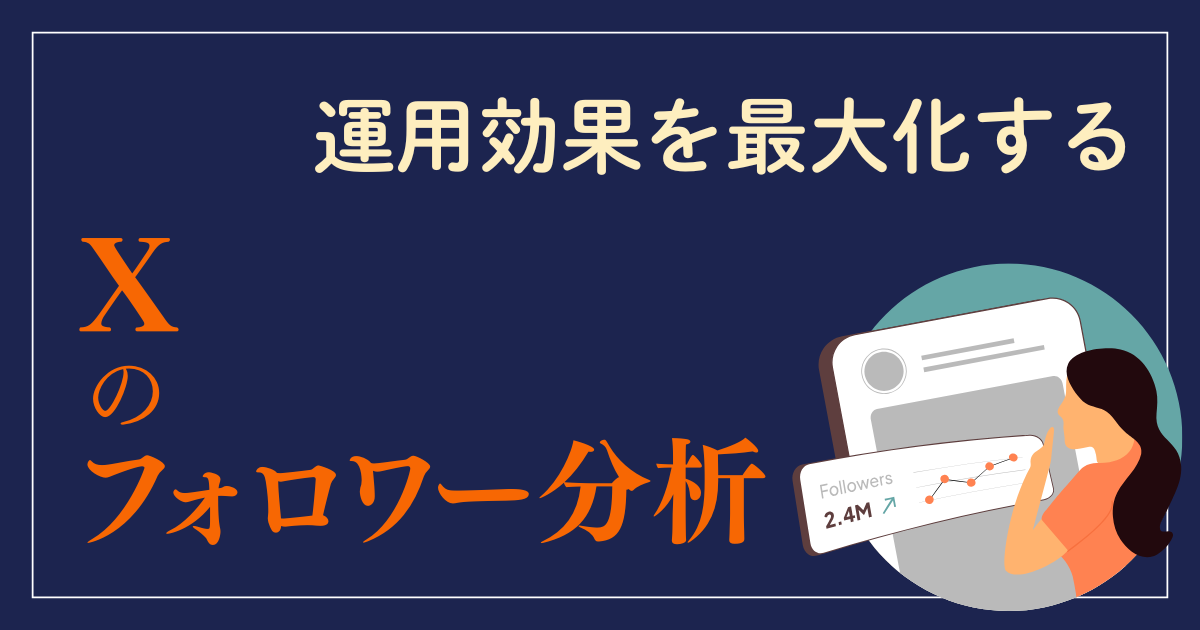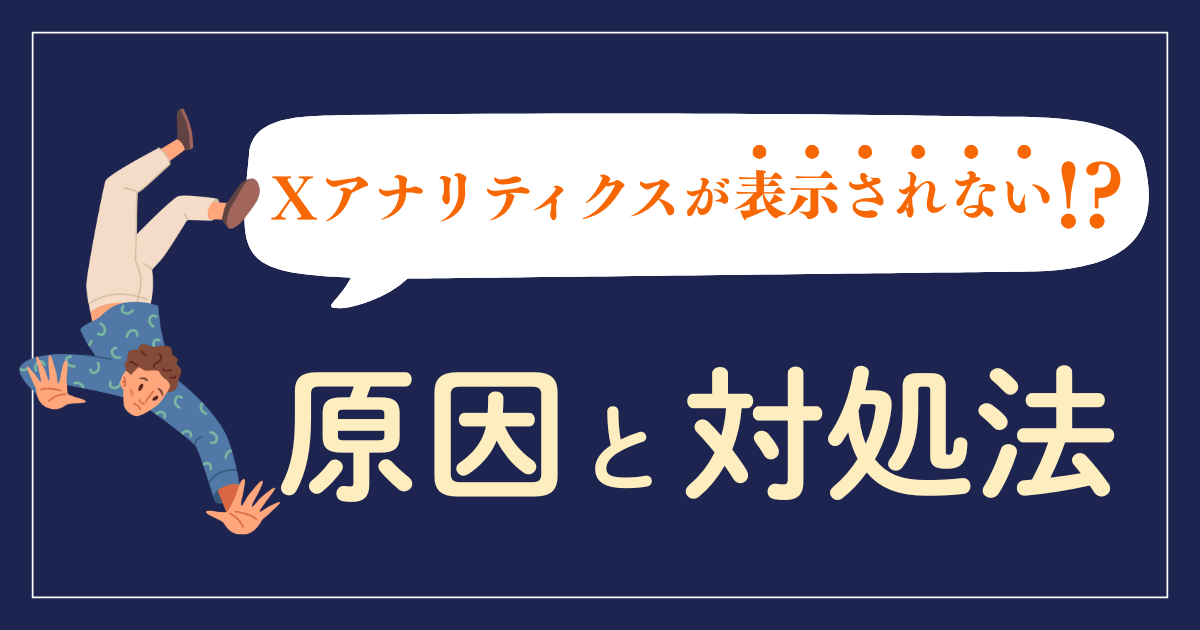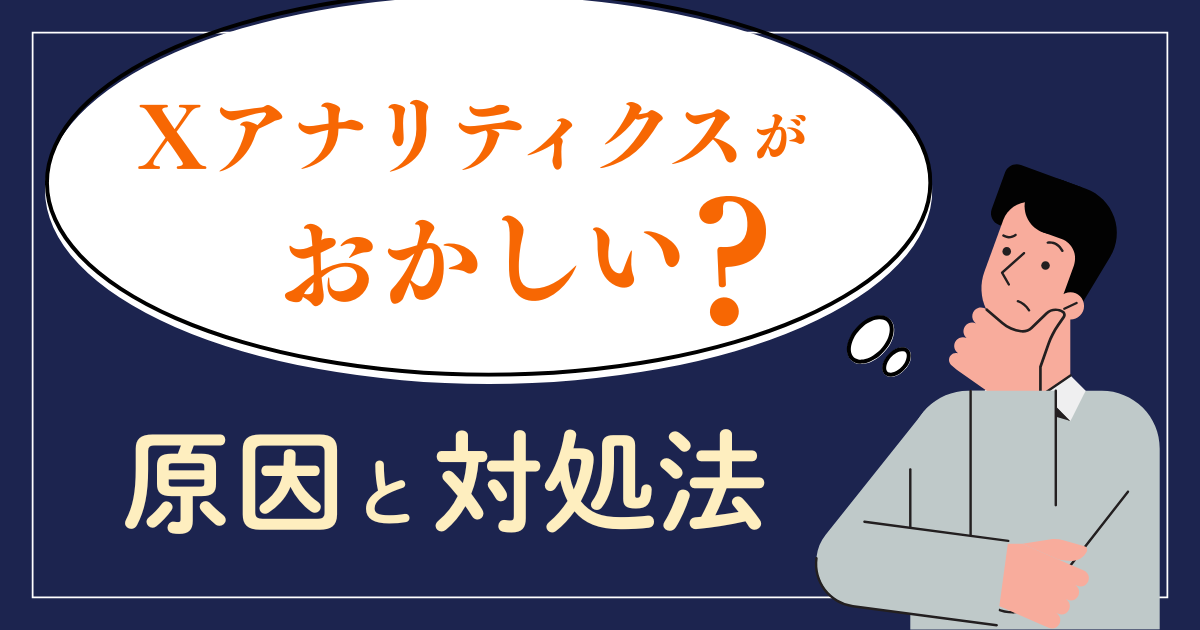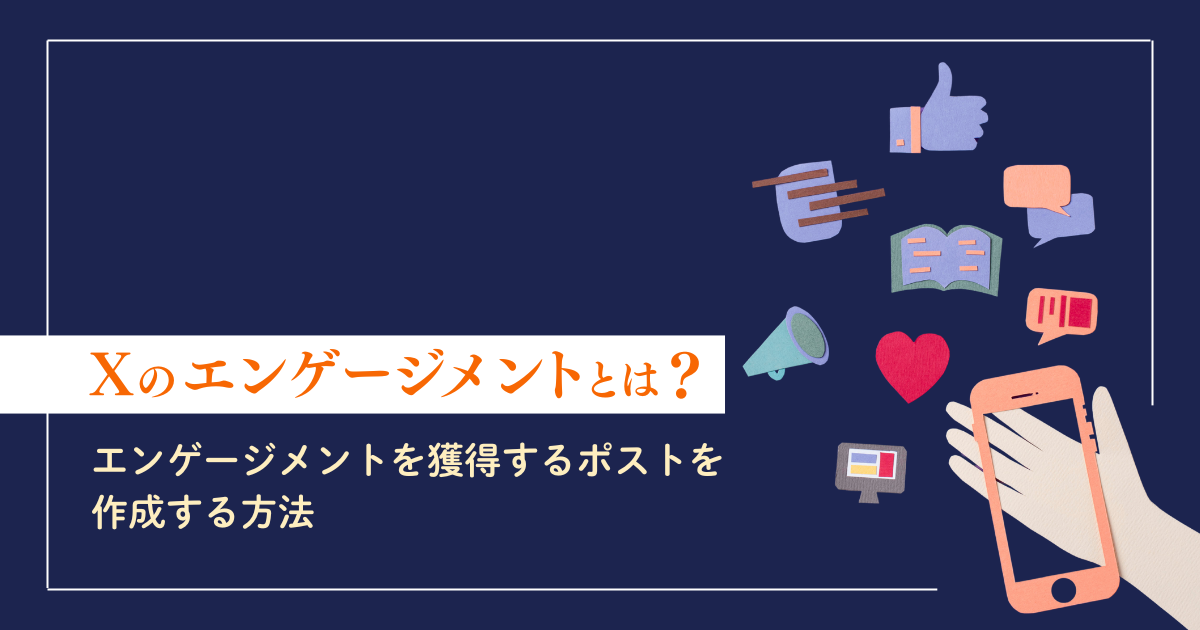X(Twitter)をビジネス活用する上で、自社アカウントの状態を客観的に把握する「アカウント分析」は欠かせません。ポストの反応やフォロワー属性だけでなく、アカウント全体の傾向や強み・弱みを可視化することで、運用の方向性や改善策が見えてきます。
本記事では、アカウント全体を分析する際の視点や活用ツール、分析結果をどう改善につなげるかまでをわかりやすく解説します。
X(Twitter)のアカウント分析とは?
X(Twitter)の運用成果を上げるためには、ただ投稿を続けるだけでなく、「今のアカウントがどんな状態にあるのか」を定期的に見直すことが重要です。
そこで役立つのが「アカウント分析」です。これは投稿単体では見えない全体的な傾向やユーザーの動き、エンゲージメントの質を可視化し、次の戦略につなげるための判断材料を提供してくれます。ここではまず、アカウント分析とポスト分析の違い、分析から得られる主な指標、その活用場面を詳しくお伝えします。
アカウント分析とポスト分析の違い
X(Twitter)において、「ポスト分析」は個別投稿のパフォーマンスを細かく見るものであるのに対し、「アカウント分析」はその集積としての全体像を見る作業です。
たとえば、ポスト分析では「Aという投稿が何人に表示され、何件のいいねやRTがあったか」「リンクのクリック率はどうか」などを評価します。これは短期的な反応や投稿の良し悪しを判断するのに向いています。
一方、アカウント分析では「直近30日間でフォロワーがどれだけ増えたか」「インプレッションが月単位で増えているか」「プロフィールへのアクセスは投稿数と比例しているか」など、より中長期的なトレンドを把握します。
つまり、ポスト分析が「点」の評価であるのに対し、アカウント分析は「線」や「面」の評価であるとも言えます。どちらか一方だけでなく、アカウント運用の目的に応じて両方の視点を組み合わせることが、成果につながる重要な鍵になります。
アカウント分析でわかる主な指標と意味
アカウント分析では、投稿単体では見えにくい「アカウント全体の動き」や「中長期的な変化」を把握できます。X公式アナリティクス上で見られるものもあれば、CSV出力が必要な指標もあるため、確認方法も含めて把握しておきましょう。
- フォロワー数と増減の推移
フォロワー数は基本的な指標ですが、重要なのは「いつ・なぜ増減したか」という傾向です。ポスト分析では特定の投稿が原因で増減したかを見ますが、アカウント分析では月単位・週単位での変動や、その背景にある施策の影響を把握します。X公式アナリティクスでは過去28日間の推移を確認でき、CSVを使えば日別の変化も詳細に追えます。 - インプレッション数
投稿が表示された回数を示すインプレッションも、単体ではなくアカウント全体で集計することで、月ごとの認知度や露出量の変化が見えてきます。投稿数が少なくてもインプレッションが維持されていれば、投稿の質や拡散力が高い可能性があります。こうした変化の背景を探ることで、次の運用方針が見えてきます。 - エンゲージメント数とエンゲージメント率
いいねやリツイートなどの反応は、投稿ごとにも確認できますが、アカウント全体でのエンゲージメント率の平均推移を見ることで、長期的なユーザーの反応傾向が掴めます。徐々に反応が鈍っている場合は、投稿内容の鮮度やフォロワー層の変化を疑うべきです。アナリティクス画面では全体の数値のみ表示されますが、CSVで期間ごとの平均を算出することで深い分析が可能になります。 - プロフィールアクセス数
投稿からアカウントへの関心がどれほどあったかを見る指標です。フォローや外部リンク遷移の前段階にあたる重要なアクションで、関心はあるが行動に至らない原因を探るヒントにもなります。プロフィール訪問数の変化を見ることで、アカウントの見せ方や投稿の訴求力を見直すきっかけになります。 - 外部リンクのクリック数
投稿内に含まれるリンクのクリック数は、基本的にポスト分析の対象です。一方で、アカウント全体として「どれくらい外部サイトへ送客できているか」を把握する場合は、期間を通じたリンククリック数の傾向を集計・分析する必要があり、これはアカウント分析の視点にあたります。
ただし、X公式アナリティクスでは期間全体のリンククリック数は画面上に表示されず、CSVをダウンロードして集計しなければなりません。また、プロフィール欄に設定したリンクのクリック数はX側で取得できないため、パラメータ付きURLや短縮URLなど、外部ツールを使った工夫が必要です。
このように、アカウント分析では「個別の結果」ではなく「全体の傾向」や「変化の理由」に注目することで、より本質的な改善が可能になります。
どんな場面でアカウント分析が役立つか
アカウント分析は「定期的なモニタリングツール」としてだけでなく、運用のあらゆる場面で効果的に活用できます。特に役立つ場面は次の通りです。
- 施策の振り返り
キャンペーン投稿やイベント告知など特別な施策を行った後は、アカウント全体にどのような影響が出たかを確認する必要があります。たとえばフォロワー増減、プロフィールクリック数、リンク遷移の変化などを分析し、施策の成果と改善点を洗い出します。 - 成長戦略の立案
今後のアカウント方針を考える際に、現状の数値をもとに「何が強みで、どこに課題があるか」を客観的に把握できます。新しい方向性を決める材料として有効です。 - フォロワー減少時の原因調査
急にフォロワーが減った場合も、アカウント分析を通じて「反応が減った投稿」「投稿頻度の変化」「炎上や誤解を招く表現」などの要因を特定できます。早期対応が可能になります。 - プロジェクトや担当者交代時の引き継ぎ資料として
運用履歴や成果を数値として残せるため、チームでの連携や外注パートナーへの共有にも活用できます。
このように、アカウント分析は「施策前」「施策中」「施策後」すべてのタイミングで活かすことができ、継続的な改善サイクルを作るうえで不可欠な分析です。
分析に使える代表的なツールとその特徴
アカウント分析を行うには、客観的なデータに基づいた評価が欠かせません。そのために活用できるのが、X(Twitter)の提供する公式ツールや、一部の外部分析ツールです。目的に応じて適切なツールを選ぶことで、数値の可視化や改善施策の精度が大きく向上します。
このセクションでは、X公式アナリティクスの使い方とコツ、外部ツールの特徴、無料・有料ツールの使い分けについて解説します。
X公式アナリティクスの使い方と活用のコツ
Xが公式に提供する「アナリティクス」は、投稿ごとのデータはもちろん、アカウント全体の動きも把握できる標準的な分析ツールです。基本無料で使える上、UIもシンプルなため、初めての方にもおすすめです。
【主な機能】
- フォロワーの増減推移(過去28日間)
- ツイート全体のインプレッションとエンゲージメント
- 最も反応の高かった投稿(トップツイート)
- プロフィールへのアクセス数と外部リンククリック数
【使い方のポイント】
- 月ごとの推移を定点観測する
「日々の数字」に振り回されず、28日間比較を使って月単位の変化を観察することで、より冷静にトレンドを捉えることができます。 - トップツイートから傾向を読み取る
反応の大きかった投稿を集中的に分析し、文体や内容、時間帯などの共通点を見出しましょう。これは今後の投稿改善に直結します。 - プロフィールアクセスとリンククリックに注目する
単に投稿がバズったかどうかではなく、どれだけプロフィールや外部ページに誘導できたかを見ることで、コンバージョン導線の評価が可能になります。
なお、X公式アナリティクスは、現在「Xプレミアム」以上の有料プランでのみ利用可能となっています。ビジネスでXを利用する場合は、加入を検討すべきでしょう。
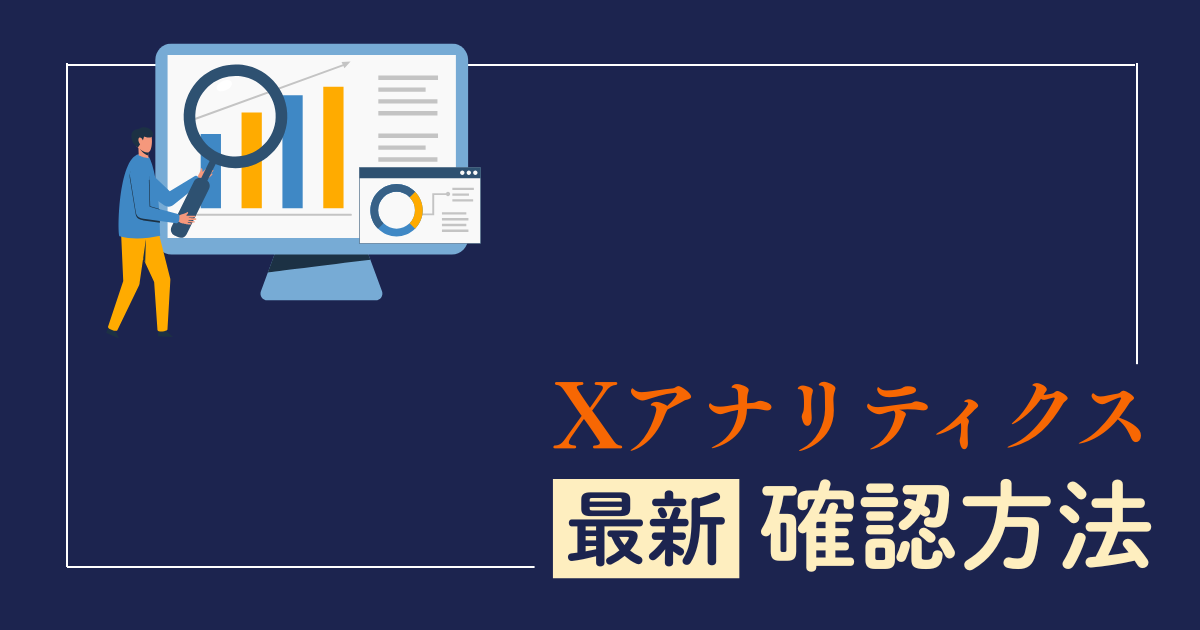
外部ツール(例:SocialDogなど)の強みと選び方
X(Twitter)運用におけるアカウント分析では、公式アナリティクスだけでカバーしきれない部分を補うために、外部ツールの活用が大きな力になります。たとえば、フォロワーの推移やインプレッションの変化を長期的に追跡できたり、投稿ごとの反応傾向を横断的に比較できたりといった高度な分析が可能になります。
また、CSV出力やグラフ表示によってデータの視覚化や社内共有がしやすくなり、改善アクションに結びつけやすいのも外部ツールの強みです。さらに、複数アカウントを一元管理できる機能を備えたツールも多く、企業アカウントの統合的な運用や、複数ブランドの展開にも対応できます。
こうした外部ツールの中でも、特に多くの企業や個人事業主に利用されているのが「SocialDog」です。
【SocialDogの強み】
- 投稿後の反応(いいね数・リポスト数など)は自動で記録され、グラフで可視化できるため、反応の推移を把握しやすい
- フォロー・フォロワーの関係や、非アクティブなユーザーの管理がしやすく、アカウント整理に役立つ
- すべて日本語対応の画面設計とサポート体制が整っており、初心者でも安心して使える
- 過去の投稿データをもとに、反応の良かった時間帯を提示してくれるため、投稿タイミングの最適化に役立つ
- 投稿ごとの反応を比較しやすく、エンゲージメントの傾向がつかみやすいため、改善ポイントが明確になるれる
【ツール選びのポイント】
外部ツールを選ぶ際は、以下のような基準で検討すると自社に適したものを見つけやすくなります。
- 過去データをどの程度さかのぼれるか(例:7日、30日、無制限など)
- 投稿分析とあわせて予約投稿・フォロワー管理などが必要かどうか
- CSV出力やグラフなど、レポート共有に適した機能があるか
- チームでの利用に必要な「複数ユーザー管理」や「アカウントの権限設定」に対応しているか
- 無料で始められるか、また有料プランの費用対効果が合うかどうか
これらのポイントを整理しておくと、数あるツールの中から「本当に自社に合った1本」を選びやすくなります。まずは無料プランから試して使用感を確認し、必要に応じて有料プランに切り替えるのがおすすめです。
無料ツールと有料ツールの使い分け方
アカウント分析に活用できるツールには、無料で利用できるものと、有料のプランが必要なものがあります。すべての機能をフルに使える有料ツールに魅力を感じる一方で、「コストに見合う成果が出るかどうか」を見極めることが重要です。
【無料ツールの利点】
- 初期コストが不要で、すぐに導入できる
- 基本的な数値(インプレッション、エンゲージメントなど)は十分把握可能
- 小規模運用や個人事業主にとっては必要十分
【有料ツールの利点】
- 過去データの保存期間が長く、長期的トレンドが掴みやすい
- 投稿のパフォーマンス比較やA/Bテスト機能を持つものもある
- チームでの運用に適した管理・共有機能が充実
【使い分けの基準】
- 「まずは試したい」「小規模で運用中」という段階であれば無料ツールでも十分対応可能です。
- 一方で、複数アカウントを一括管理したい、チームでKPIを共有したい、レポート出力を効率化したいといったニーズがある場合は、有料プランの検討をおすすめします。
ツール選びで迷ったときは、「どの指標を定期的に確認したいか」「どれくらいの粒度で分析したいか」を先に整理しておくと、自社に合った選択がしやすくなります。
アカウント分析でチェックすべき4つのポイント
アカウント分析を効果的に行うためには、どの数値をどう見ればよいのかを明確にしておくことが重要です。特にX(Twitter)をビジネス利用する際は、単に「フォロワーが増えた」「バズった」といった感覚ではなく、戦略的に見るべきポイントがあります。
ここでは、成果を出すためにぜひ押さえておきたい4つの注目指標を、それぞれの意味や活かし方とあわせて詳しく解説します。
フォロワー数と増減の傾向
フォロワー数は、アカウント全体の注目度や信頼性を示す最も基本的な指標です。ポスト分析では特定の投稿がきっかけで増えた・減ったといった一時的な変動を捉えることはできますが、「フォロワーが増え続けているのか停滞しているのか」「キャンペーン後に離脱が増えていないか」などの中長期的な傾向を読み取るには、アカウント単位での分析が欠かせません。
たとえば、ある1投稿がバズったことで一時的にフォロワーが増えたとしても、アカウント全体のフォロワー維持率が悪ければ、定着には至っていない可能性があります。こうした離脱傾向は、ポスト単体の分析では見落とされがちです。逆に、目立ったバズがなくても、フォロワー数が緩やかに増え続けている場合は、コンテンツの一貫性やアカウント自体の信頼性が評価されているといえます。
また、月単位や四半期単位でのフォロワー推移を可視化すると、「どの時期に停滞があったのか」「運用施策の転換が影響しているのか」など、全体像を踏まえた施策検討が可能になります。こうした分析は、投稿単体を評価するポスト分析ではなく、アカウント分析だからこそ得られる視点です。
エンゲージメント率と変化の背景
エンゲージメント率(=投稿に対する反応率)は、投稿ごとに評価することもできますが、アカウント全体でのエンゲージメント率の「平均値」や「推移」を見ることで、より深い洞察が得られます。ポスト分析では「どの投稿が反応を得たか」を知ることはできても、「ここ最近、反応が鈍くなってきていないか」といった長期的な反応の変化までは見えにくいからです。
アカウント分析では、複数の投稿のエンゲージメント率を俯瞰し、一定期間の平均値や中央値をもとに、「今のコンテンツ方針はユーザーに届いているのか」「最近の変化が投稿内容とどう関係しているのか」などを見極めます。
たとえば、ある期間だけエンゲージメント率が下がっている場合、それが投稿内容の問題なのか、投稿時間帯のズレなのか、ユーザーの動きによるものなのかを、全体傾向から逆算することができます。
さらに、週次・月次単位でエンゲージメント率を追い続けることで、「反応の鈍化を早期に察知する」「改善施策の効果を数値で検証する」といった、戦略的な運用につなげることが可能になります。これは単発の投稿に着目するポスト分析とは一線を画す、アカウント分析の重要な役割です。
投稿頻度と反応の関係
投稿頻度とユーザーの反応との関係も、アカウント全体の流れを見ないと見誤ってしまう指標のひとつです。ポスト分析では「この投稿は反応が良かった」と判断できますが、「投稿頻度を増やした結果、反応全体がどう変化したのか」といった行動パターンの変化は、アカウント単位の集計がなければ評価できません。
たとえば、1日1回の投稿から1日2回に変更したとき、個々の投稿だけを見て反応がバラついているように見えても、アカウント全体の平均エンゲージメント率やプロフィールクリック率が上がっていれば、頻度アップが成功している可能性があります。逆に、投稿数は増えても反応率が下がり、プロフィール閲覧も減っているようであれば、ユーザーの疲弊や投稿の希少性の低下が影響していると考えられます。
また、過去3ヶ月間の投稿数と反応傾向を照らし合わせると、「頻度を落とした時期のほうがエンゲージメントが高い」「特定の曜日だけ反応が伸びやすい」といった法則性が見えてくることもあります。こうした視点から、無理のない更新スケジュールを設計することは、長期運用において非常に大きな意味を持ちます。
投稿のパフォーマンスを“個別”ではなく“全体的”に捉え、継続的な成果を導き出すための判断材料として投稿頻度を見る――それがアカウント分析の視点です。
プロフィールのクリック率と遷移導線
プロフィールのクリック率や外部リンクの遷移率も、アカウント分析で重視すべき指標のひとつです。これは、ユーザーが投稿をきっかけにアカウントに関心を持ち、「もっと詳しく知りたい」と感じたときに現れる行動です。ポスト分析では投稿単体の反応は見えても、「アカウント全体への関心」や「他チャネルへの誘導状況」までは測ることができません。
アカウント分析では、「投稿→プロフィール→外部リンク」という導線を“流れ”として評価します。たとえば、投稿のインプレッションは多いのにプロフィールクリック率が低ければ、投稿内容とプロフィールの内容や見せ方にギャップがある可能性があります。一方で、プロフィールクリックが多く、さらにリンクのクリック数も伸びていれば、アカウントの信頼性や価値がしっかり伝わっている証拠となります。
また、これらの数値を月ごとに追っていくことで、「プロフィールを改善したことでリンククリックが増えた」「投稿頻度を上げたらプロフィール訪問数が減った」といった変化の背景も見えてきます。このような変化の“傾向”や“因果関係”を把握することができるのが、アカウント分析ならではの強みです。
ビジネス目的でXを活用している場合、プロフィール欄は「成約につながる最後の接点」として機能します。だからこそ、単にアクセス数を測るだけでなく、その導線が十分に機能しているかを、アカウント全体の動きの中で捉えることが重要です。
分析結果を運用改善にどう活かすか?
アカウント分析で得たデータは、見て満足するものではありません。それらの数字をもとに「どう改善するか」「どんな判断をするか」が重要です。運用成果を高めるためには、分析を日々の運用や戦略に落とし込む“活かし方”が鍵になります。
このセクションでは、実際の改善につなげるためのステップを3つの観点で解説します。
目標設定とKPIの再設計
まず重要なのは、「何を目的として運用しているのか」「そのためにどの指標を追うのか」という軸を再確認することです。X運用では、フォロワー数・インプレッション数・エンゲージメント率・リンククリック数など、さまざまな指標が取得できますが、目的に合っていなければ、いくら分析しても改善に結びつきません。
たとえば、「問い合わせの増加」を目的とする場合は、プロフィールのクリック率や外部リンクの遷移数に着目すべきですし、「ブランド認知の拡大」が目的であれば、インプレッション数や投稿ごとのリーチ数が重要になります。アカウント分析はこれらの指標を中長期的に把握できるため、KPI設計の精度を高める材料になります。
また、分析結果を見てKPIが現実とズレていると感じたら、運用の段階に応じてKPIを柔軟に見直すことも必要です。アカウントが立ち上げ期なのか、成長期なのか、成熟期なのかによって、注視すべき指標も変わってきます。
数字を「結果」として捉えるだけでなく、「次の目標」を設計する起点とする――それがアカウント分析を活かす第一歩です。
ターゲットに響く投稿内容・時間帯の調整
アカウント分析の中で、投稿の平均的なエンゲージメント率や反応の傾向を把握できれば、投稿の内容やタイミングを調整する根拠が得られます。ポスト単体では「この投稿は反応がよかった」という事実しか見えませんが、アカウント全体の傾向を見ることで、「どのタイプの投稿が、どの時間帯に、どのくらい反応されやすいか」という再現性あるパターンを見つけることが可能です。
たとえば、月ごとの投稿傾向を分析して、「画像付き投稿は朝の方が反応が良い」「テキスト中心の投稿は夕方が強い」「金曜の投稿はエンゲージメントが低下する」といったデータがあれば、それを踏まえて投稿スケジュールを最適化できます。これにより、試行錯誤ではなく“仮説と検証”の運用が実現できます。
このように、アカウント分析を通じて「自社のフォロワーが反応しやすい投稿スタイルと時間帯の傾向」を把握することは、今後の発信力を高めるうえで非常に重要です。日々の投稿を“感覚”ではなく“根拠”をもって調整していくことで、運用全体の質が高まり、成果にもつながりやすくなります。
アカウントの方向性を定める戦略の見直し
最終的にアカウント分析は、「そもそもこのアカウントは、誰に・何を・どう伝えるのか」という戦略そのものの再考に活かすことができます。これは、日々の投稿単位で見えることではなく、全体の傾向・推移・ユーザー行動を長期視点で見て初めて気づけるものです。
たとえば、思ったよりもプロフィール閲覧数が少ない場合は、認知フェーズの発信に偏っていないかを見直す必要があります。また、フォロワー数は増えているのにエンゲージメント率が低下している場合は、「誰に響いているのか」がズレてきている可能性もあります。
こうした気づきをもとに、「今の運用方針はターゲットに合っているか?」「アカウントの見せ方は一貫性があるか?」を問い直すことで、次の改善ステップへ進めるのがアカウント分析の価値です。
分析は、日々の施策の振り返りだけでなく、アカウント自体の“舵取り”を行うための重要な材料になります。
まとめ
X(Twitter)アカウントの成果を高めていくには、感覚や勘に頼るのではなく、データに基づいた運用が大切です。アカウント分析を取り入れることで、投稿単体では見えにくい“アカウント全体の動き”や“変化の兆し”をつかみやすくなります。
本記事では、アカウント分析の基本的な視点から、見ておくべき指標、分析に使えるツール、そして改善への具体的な活かし方までを解説しました。
- ポスト分析との違いを理解し、アカウント全体を俯瞰する
- フォロワー数やエンゲージメント率、クリック率などを継続的にチェックする
- 分析から得られた気づきを、KPIや運用方針の見直しに反映させる
こうした取り組みを積み重ねることで、アカウントは少しずつ、着実に前に進んでいきます。
ぜひ、本記事でご紹介した視点を取り入れて、成果につながるX運用につなげていただけましたら嬉しいです。